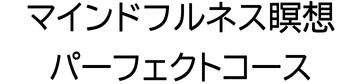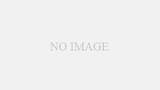自分の関わっている宗教・宗派、団体以外を否定したり見下すようなことを見聞きしますが気をつけたいことです。仏教を信じている人が仏教が最高で他はだめだと排他的な言動をするのを見聞きすることがありますがそれもそうです。
前のページの講義「正しい見解、手放すべき見解」で手放すべき見解の一つに「見取見(けんじゅけん):自らの見解だけを最高とし他の見解を誤りとする」ことがあると学びましたが、まず読んでほしいアショーカ王の文を紹介します。
仏教を広めたアショーカの場合
前ページの「仏教の歴史」で、インドの紀元前3世紀のマウリヤ朝のアショーカ王が仏教を保護して広めた、アショーカ王がいなかったなら今のように仏教はなかった、アショーカ王は仏教だけでなくバラモン教やジャイナ教なども認め尊重して援助したと紹介しました。
アショーカ王の造った今も現存している王の石碑の1つに次のように記されています。
人は、自らの宗教のみを信奉して、他の宗教を誹謗することがあってはならない。そうではなくて、他の宗教も敬わねばならない。
そうすることにより、自らの宗教を成長させることになるだけではなく、他の宗教にも奉仕することになる。そうしなければ、自らの宗教に墓穴を掘り、他の宗教を害することになる。
他の宗教を誹謗するものは、自らの宗教に対する信心から、「自分の宗教を称えよう」と思ってそうする。だが実際には、そうすることで自らの宗教をより深刻に害している。 それゆえに、和合こそが望ましい。誰もが、他の人々が信奉する教えを聴こう、聴くようにしよう。
そして、ブッダは次のように説いたと言われます。
ブッダの場合
スッタニパータ893
(前略)他の人の説を「愚かである」「不浄の教えである」と説くならば、かれは自ら確執をもたらすであろう。
スッタニパータ894
(前略)一切の断定を捨てたならば、人は世の中で確執を起こすことがない。
信仰のある人が「これは私の信仰です」と述べる限りにおいて彼は真実を保持している。
しかし、そこから一歩進んで「これのみが真実であり、他はすべて偽りである」と断言することはできない。
言い換えれば、人は自分の好きなこととを信じる権利があり「私はこう信じています」と述べて差しさわりはない。その限りにおいて、彼は真実を尊重している。
しかし自らの信心あるいは信仰から自分が信じていることのみが真実で他のすべては偽りであると主張することは許されない。
ある一つの見解に固執し他の見解を見下すこと賢者はそれを囚われと呼ぶ。
ブッダには次のような話もあります。
ブッタと同時代にインドで開かれたジャイナ教の開祖のニガンタ・ナータブッタは、業(カルマ)についてブッダとは異なる見解でした。そこで彼の信者だったウバーリをナーランダにいた遣わしてブッダに論争を挑ませました。
論争の末、ウバーリはブッダの見解が正しく自分の師の見解が間違っていることを確信して、ブッダに弟子入りを願い出ました。するとブッダはどうしたか?
ブッダはウバーリに「慎重に検討することはいいことである」と急いで決断せずにもう一度考えるように促したのです。そして 再度、ウバーリが弟子入りを請うとこれまで師事した師たちを従来通り尊敬して支持するようにと促しました。
ブッダは、見解の相違について批判(比べた判断)を語ることはあっても、〇〇教はとか〇〇さんはだめというように、まるまる否定するようなことはなさいませんでした。
バラモン教も否定せず
ブッダはバラモン教を回復しようともしていましたが、どのような方法でそうしたか?
バラモン教など他の宗教で使われている「言葉」の元にある信仰を否定はせず、その言葉が善い方向としての意味を持つなら用語として活かして、その言葉に含まれている間違った面だけを取り去るような示しかたをしました。
また、バラモン教の教えの善い意味の部分を引用して善い方向に活かし役立てるよう教えたり、正しく善い教えは正しさ善さを普遍的なものとして教えたりしました。
バラモン教が堕落してしまっている現状について、元々の教えは正しいとして、その元の善い教えとはどういうものかと示す方法を取りました。
例えば、仏教とキリスト教
上座部仏教のワールポラ・ラーフラ師の書『ブッダが説いたこと』には次のように書かれています。
人間はものを識別しようとする傾向が強いあまり、誰にでも共通する性質とか感情にまで個別的名称を付けて識別している。
たとえば「慈善」という行為にしても、「仏教的」慈善と「キリスト教」的慈善とまるで異なったものであるかのように呼び、他の個別的名称が付けられた慈善を見下したりする。
しかし慈善には宗教による違いなどありえない。慈善はキリスト教のものでもなく、仏教のものでも、ヒンドゥー教のものでも、イスラム教のものでもない。
母親の子どもに対する愛は、仏教的でもキリスト教的でもなく、母性愛である。
実際のところ、真実を理解するのに、それがブッダに由来するものなのか、誰か別人に由来するものかを知る必要はない。肝心なことは目の当たりにし、理解することである。