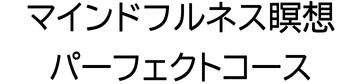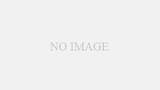六波羅蜜(ろくはらみつ)は大乗仏教における6種類の実践徳目で「六度」とも言われます。
インドの古いパーリ語で書かれた釈迦の過去世物語のジャータカなどにすでに記されていますが、初期の大乗仏教の経典がそれを集大成しました。
次の6つです。六波羅蜜は修行レベルのことにもなっていますから、そのように読んでください。
- 布施波羅蜜
- 持戒波羅蜜
- 忍辱波羅蜜
- 精進波羅蜜
- 禅定波羅蜜
- 智慧波羅蜜(般若波羅蜜)
波羅蜜はこの6種類の徳目の完成状態のことで、6種類の中では智慧波羅蜜(般若波羅蜜)が肝心かなめとされ、ほかの5つの波羅蜜はこれを得るための準備手段となります。
波羅蜜はサンスクリット語の「パーラミター」、彼岸(迷い)から此岸(覚り)に到達する道、菩薩が仏になるために行う修行のことですが、実業家であり思想啓蒙者として著名だった稲盛和夫氏は次のように述べています。
お釈迦さまの説かれた六波羅蜜という修行の方法についてもみなさんに説きました。それはまさに、私がいつも話をしてきた、こういう経営哲学をもたなければなりませんということと同じなのです。普通の人間が生きるための知恵として、ぜひ取り入れるべきだと私は信じます。
なお、稲盛氏は禅の臨済宗の在家得度を受けて、修行僧と共に修行を重ねた人でもあります。
布施波羅蜜
他者に財物などを施したり利益になるよう教えを説くことなど、与えることで、財施、法施、無畏施の3種類に分けて説かれます。
- 財施:金銭や衣服食料などの財を施す
- 法施:仏の教えを説く
- 無畏施:患難にあっている人を慰めて恐怖心を除く
その他に、ステップ3で学んだ財物をともなわない七つの布施として無財の七施があります。
布施の対象者
布施によって布施をする相手をどのような人にするかも大切です。不適切なことをすると、その人が堕落してしまうこともあります。仏教では「福田」と言い、田にたとえて、布施を行なうとき、相手に多くの福徳を生み功徳が得られるようにとします。
そして、布施は与えられる方に得るものがあるだけでなく、田に種を蒔くと自分の持っているものが減ったようではありますが、時が来ると何倍もの収穫になって戻って来ることになります。
仏や僧に対してを恭敬福田(敬田)、父母や師に対してを報恩福田(恩田)、貧者や病者に対してを貧窮福田(悲田)と言います。
持戒波羅蜜
戒を守ることです。
八正道の戒の項目もそうですが、一般の人・在家者や大乗仏教の修行者・僧は五戒または八戒を、上座部仏教の出家修行者の場合はさらに律に規定された禁戒を守ることを指します。
このプログラムは、ステップ2から守るようにしている十善戒で一般の人は項目としては十分です。
五戒
- 不殺生戒(ふせっしょうかい): 故意に生き物を殺さない
- 不偸盗戒(ふちゅうとうかい):人のものを盗まない
- 不邪淫戒(ふじゃいんかい) : 不道徳な性行為をしない
- 不妄語戒(ふもうごかい): 嘘をつかない
- 不飲酒戒(ふおんじゅかい):酒類を飲まない
八戒は八斎戒とも言います。
五戒に「正午以降は食事をしない」「歌舞音曲を見聞きせず装飾品、化粧・香水など身を飾るものを使用しない」「高台や贅沢な寝具や座具でくつろがない」の3つが加わります。
上座部仏教の出家修行者の場合は具足戒(ぐそくかい)と言います。
男性は250、女性は348の戒があり、一番重いのは波羅夷(はらい)の分類に入り、男女の交わり、殺人、大泥棒、悟っていないのに悟ったという大嘘の4つで、破ると永久追放になります。
忍辱波羅蜜
忍辱(にんにく)は耐え忍ぶことです。思い通りにならないこと、あらゆる侮辱や迫害も耐え忍んで怒りの心をおこさないことです。
これを実践することによって、すべての障害から身を保護できるので「忍辱の衣」「忍辱の鎧」とも言われます。
精進波羅蜜
悪を断ち善行を実践し、雑念を去って仏道修行にひたすら励む積極的な姿勢のことですが、八正道の正精進に該当します。
正精進は次の四種類の正しい努力(四正勤)を心を励まし努めることです。
正精進
- まだ生じない(していない)悪を生じない(しない)ように努める
- すでに生じた(してしまった)悪は断(しないよう)に努める
- まだ生じない(していない)善を生起(するよう)に努める
- すでに生じた(した)善を維持(していくこと)に努める
禅定波羅蜜
特定の対象・ことに心を集中して散乱する心を安定させることです。
八正道の定の項目のうち、正精進は上記の精進に入りますが、正念と正定がこれに該当します。正しくは瞑想の取組みが必要です。
智慧波羅蜜(般若波羅蜜)
すべての事物や道理を明らかに見抜く深い智慧のことで、この智慧を般若と言います。八正道では正見が進展した正智に該当します。
ほかの五つの波羅蜜は、この般若波羅蜜を成就するための階梯と位置づけられますが、八正道も正見の成就を全体として目指すように六波羅蜜でも全体として般若波羅蜜の成就を目指します。