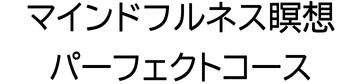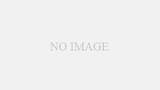このページまでにも「パーリ語仏典」と出てきましたが、パーリ語仏典について説明します。このプログラムは、仏教としてパーリ語仏典を主に元にしています。
お釈迦様が説いただろうということが書かれているのが仏典です。「だろう」というのは、お釈迦様自身は何一つ書き残してはいないからです。
お釈迦様が亡き後、仏教は多岐に多くの仏典がつくられて、その数は8万4千巻とも言われます。
発見され現存している最古の仏典はインドの古いパーリ語という言語で書かれているものでパーリ語仏典と言います。そのパーリ語仏典もお釈迦様が説いたことそのものではない面がありますが、お釈迦様が説いたことに比較的近いと考えられています。
パーリ語仏典は、お釈迦様が説いたことの経典の「経蔵」と、戒律の集成の「律蔵」、経典の説明・注釈がまとめられた「論蔵」で、あわせて「三蔵」と言います。
経蔵は5つのニカーヤ(部)に分かれています。
パーリ語経典の5つのニカーヤ(部)
ニカーヤは次の通りです。
- ディーガ・ニカーヤ(長部経典)
- マッジマ・ニカーヤ(中部経典)
- サンユッタ・ニカーヤ(相応部経典)
- アングッタラ・ニカーヤ(増支部経典)
- クッダカ・ニカーヤ(小部経典)
クッダカ・ニカーヤ(小部経典)には
- ダンマパダ(法句)
- ウダーナ・ヴァルガ(感興偈)
- スッタニパータ(経集)
- テーラガーター(長老偈)
- ジャータカ(本生物語)などがあります
このプログラムでは『ブッダの真理のことば、感興のことば』中村元訳などから、一部ひらがなに変えて引用しています。